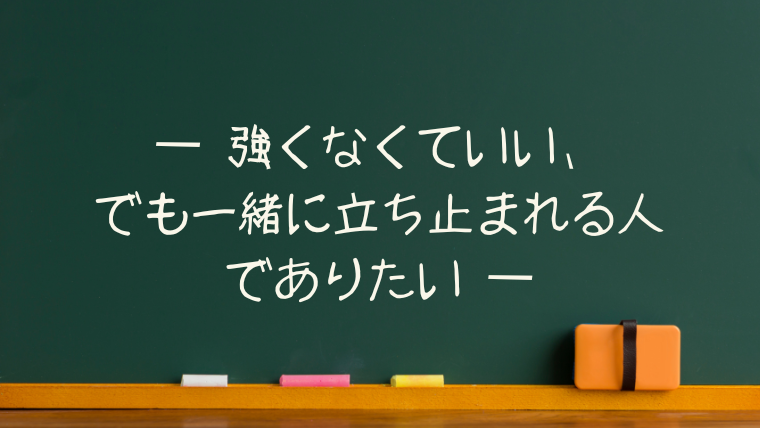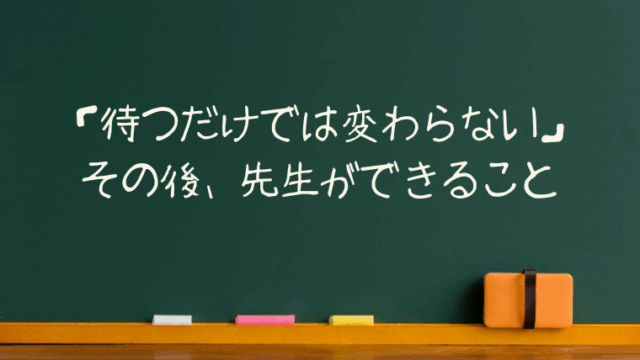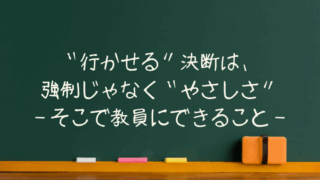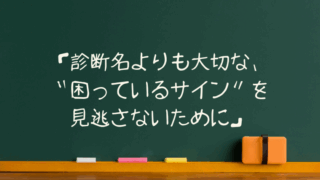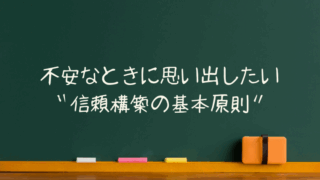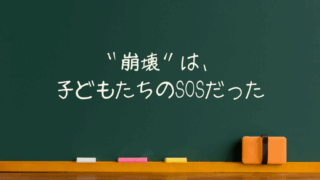こんにちは。ねこまるです。
小学校で発達障害児や特別支援学級児童の支援員をしながら
先生がたのサポートする仕事をしています。
「自分はリーダーに向いていないかも」
「いつも正解を出せない自分が情けない」
そんなふうに感じている教員や、教育現場で責任を担う方に向けて、この記事を書いています。
実は私も、支援員として日々子どもたちと接しながら、先生たちの葛藤や迷いに何度も触れてきました。
この記事では、「リーダー=強い存在」という固定観念から一歩離れて、
“一緒に困ってくれる人こそ、本当に信頼されるリーダー”という視点を軸に、
自分を責めないためのヒントをお伝えします。
1. なぜ「グレーゾーンの子ども」の接し方に悩むのか

私たち教育に携わるものが、「教員に向いていないかも」と思うのはたいてい
「うまく指導できない」と思う瞬間です。
そして、うまく指導できない時というのは、いわゆる「グレーゾーン」といわれる子どもたちの対応をしている時なのではないでしょうか。
「グレーゾーン」という単語はいつしかよく聞くようになりました。
「グレーゾーンの子」とは、発達障害の診断基準に完全には該当しないものの、学習・行動・対人関係などで困り感がある子どものことを指す非公式な表現です。医療的な診断名ではなく、主に教育現場や子育ての場面で使われる実務的な言葉です。
-
指示が通りにくく、授業に集中できないことが多い
-
友達との会話がかみ合わず、トラブルになりやすい
-
感情の起伏が激しく、些細なことでパニックになる
-
文字や計算の習得に極端な苦手さがある
-
場の空気や暗黙のルールを読むのが苦手
このような特徴を持っています。
●「グレーゾーン」とは?通常学級にいる子どもたち
「グレーゾーン」とは、診断名はつかないけれど発達特性がある子どもたちのこと。
一見すると「普通」だけど、行動や感情において支援が必要なケースがあります。
● なぜ優しくするだけではうまくいかないのか
「優しく接しよう」「寄り添おう」と思っても、うまくかみ合わず、余計に不安定になることもあります。
優しさがルールの欠如や曖昧な指示に繋がると、子どもは混乱してしまいます。
● 支援する側が疲弊してしまう理由
「もっとちゃんと対応しなきゃ」「他の先生はできてるのに」——
そんなふうに自分を責めてしまう先生がとても多いです。
完璧を求め続けることで、支援者自身の自己肯定感も下がっていく悪循環が起こります。
2. 「よかれと思った接し方」が逆効果になるとき

「よかれと思った接し方」が逆効果になるときは、よくあります。
● 自由にさせすぎて逆に不安定になった実例
例:図工の時間に「好きなもの作っていいよ」と言われた子が固まって動けなくなった。
選択肢が多すぎて、何をすればいいのか分からなかった。
● 甘やかしと支援の違いとは
「嫌ならやらなくていいよ」は、やさしさに見えて自己否定につながることも。
本当の支援は、「やってみよう」と促す枠を一緒に作ること。
● 子どもにも支援者にも必要な「安心できる枠」とは?
枠=ルール・見通し・一貫性。
子どもは“何をしていいか分からない”状況が一番不安です。
大人の「ここまでは大丈夫だよ」が、安心につながります。
3. 「優しさ」だけじゃない|グレーゾーンの子どもに必要な接し方5原則

- 「見通し」を伝える:「次は何をするか」を教えてあげる
- 「ルール」を明確にする:「やっていいこと・だめなこと」を言葉にする
- 「できたこと」をすぐ認める:「よくがんばったね」と声に出して伝える
- 「できないこと」も受け止める:「できなくても大丈夫」と表情で示す
- 支援する大人も「守るルール」を決める:支援者自身の“軸”があると子どもも安心する
4. 教室でできる!グレーゾーンの子どもへの小さなワンアクション集

「特別な支援までは必要ないけど、ちょっと気になる」
「頑張っているけど、なぜかうまくいかない」
そんな〝グレーゾーン〟の子どもたちは、どの教室にもいるものです。
でも安心してください。特別な教材やスキルがなくても、〝教室の中でできる〟ちょっとした工夫が、子どもたちの安心と安定につながります。
ここでは明日から使える「小さなワンアクション」を5つご紹介します。
- 「あと5分で始めようね」と声かけする
- 「次に何をするか」を必ず予告する
- 「これが終わったら休みだよ」とゴールを示す
- 「〇〇できたね!」と小さな達成をすぐ認める
- 今日の支援で「よかったこと」を自分にメモする
小さなアクションの積み重ねが、子どもの安心を育て、先生自身の支援スタンスも整えてくれます。
無理に変えようとしなくても、“できる工夫”を少しずつ増やしていくことが、支援の第一歩です。
5. グレーゾーンの子どもを支援するあなたへ|自己肯定感を守る考え方

「もう少し落ち着いてくれたら…」
「何度言ってもできないのは、どうしてだろう…」
そんな風に思いながら、日々グレーゾーンの子どもと向き合っているあなたは、一生懸命にその子を理解しようとしている証拠です。
● 「支援がうまくいかない」と感じたときに思い出してほしいこと
教室で、思いを込めて声をかけたのに反応が返ってこなかった日。
何度伝えても行動が変わらず、ため息をついてしまった日。
「どうしたらいいんだろう…」と、支援に迷いを感じる日。
そんな日は誰にでもあります。
そして、それはあなたが真剣に向き合っている証でもあるのです。
でも、忘れないでください。
支援とは、「変えること」ではなく、「そばにいること」から始まるということを。
「一緒に困ってくれた先生」に子どもは救われます。
あなたが“うまく支援できなかった”と思う日も、子どもは「一緒にいてくれた」ことを覚えています。
今日うまくいかなかったとしても、
「関わったこと」そのものに価値があると、自分に伝えてあげてください。
たったひとつの声かけ、
たった一瞬のまなざし、
それだけでも、子どもの心の中では“誰かが気にかけてくれた”という記憶になって残るのです。
「支援がうまくいかない」と思ったときほど、
あなたの存在が、子どもにとっての希望のひとつになっているかもしれない。
そう思って、今日を終えてもいいのです。
● 「できなかったこと」ではなく「できたこと」を見る習慣
支援の現場で、私たちはつい「できなかったこと」に目を向けてしまいがちです。
・また授業中に立ち歩いてしまった
・声をかけたのに返事がなかった
・友達とのトラブルが減らない
振り返るたびに、自分の支援が足りないのではないか…と、責める気持ちが湧いてくることもあるかもしれません。
でも、立ち止まってほしいのです。
本当に“できなかったこと”だけでしょうか?
今日、立ち歩いたのはたしかに事実かもしれません。
でも、立ち歩く前に**「やろうとした瞬間」があったかもしれない**。
返事はなかったけれど、一瞬こちらを見た目線があったかもしれない。
トラブルのあと、自分から謝ろうとする姿勢があったかもしれない。
その「一歩分の“できたこと”」に気づけるかどうかで、
子どもとの関係も、支援者としての自分の気持ちも、ずいぶん変わってきます。
支援とは、0から100を目指すことではなく、1を2に、2を3にする積み重ねです。
成長は直線ではありません。波のように揺れながら、少しずつ進んでいくものです。
子どもの変化に目を向けられる人は、自分の頑張りにも目を向けられる人です。
今日あなたがかけた一言、そっと寄り添った時間、うまくいかなかった後に悩んだ時間もすべて、支援の一部です。
「できたこと」を見る習慣は、子どもに優しくなれるだけでなく、自分にも優しくなれる習慣。
できなかったことで自分を責めるより、今日できた1つの声かけを誇りにしてください。
● あなた自身の自己肯定感を育てるワンアクション
「支援しているつもりが、こちらが消耗してしまう」
「空回りしているようで、自信がなくなる」
そんなときは、“今日自分がやった小さなこと”に目を向けてみてください。
-
「今日は〇〇くんに、“おはよう”と声をかけた」
-
「〇〇さんの困り感を見つけられた」
-
「イライラせずに最後まで話を聞けた」
たとえ子どもの反応がなかったとしても、あなたの行動には意味があります。
子どもがすぐに変わらないからといって、あなたの関わりが無意味だったわけではありません。
「できたこと」を、自分で認めること。
「まだできていないこと」も、焦らずに見守ること。
それは、子どもの自己肯定感を育てるために必要な視点であり、あなた自身の心を守るやさしさでもあります。
あなた自身の〝自己肯定感〟も守ってくださいね。
6. まとめ|子どももあなたも、大切にできる接し方を

- 優しさだけでは守れないものがある
- 枠を作ることは、子どもを信じることでもある
- 迷いながら進むあなた自身が、「真のリーダー」
困っている自分を隠さなくていい。
それを見せられることが、子どもや仲間にとって一番の信頼につながるのです。
この記事が、迷うことに不安を感じているすべての先生にとって、
「自分のままでいい」と思えるきっかけになりますように。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
他の記事も読んでいただけたらうれしいです(=^・^=)